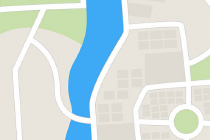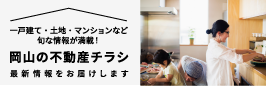木造住宅の耐用年数は何年?実際の寿命や長持ちさせる方法を解説

注文住宅で木造住宅にしたいと考えている方のなかには、実際に住める期間や耐用年数が気になっている方もいるのではないでしょうか。耐用年数とは、固定資産税の計算時に用いられるもので、実際の住宅の寿命とは異なります。
本記事では、木造住宅の耐用年数と実際の寿命の違い、木造住宅を長持ちさせるための工夫についてご紹介します。長く安心して暮らせるような木造住宅にしたい方は、参考にしてください。
目次
木造住宅の耐用年数
耐用年数とは、一般的に税制上の評価基準となる「法定耐用年数」のことです。木造住宅の場合、法定耐用年数は22年です。この年数は、住宅の固定資産税の公平な算定を目的として国により定められたもので、住宅の構造ごとに異なる基準が設定されています。
耐用年数には、法定耐用年数のほかに、物理的耐用年数や経済的耐用年数、期待耐用年数があります。ここでは、法定耐用年数を含めた4つの耐用年数の意味について詳しく見ていきましょう。
法定耐用年数
法定耐用年数は、減価償却の計算に用いられる年数です。住宅は、年数が経つごとに資産価値が減少していくと考えられており、固定資産税はその価値に応じて課税されます。
新築物件と築50年以上の物件の固定資産税が同じとなると、公平とはいえないため、建物の構造ごとに法定耐用年数を設け、年数の経過に応じて税額を調整する仕組みが導入されています。
木造住宅の法定耐用年数は、22年とされています。新築から22年間かけて、少しずつ価値が下がる前提で、減価償却の対象です。
なお、その他の法定耐用年数は下記のとおりです。
- 重量鉄骨造(骨格材肉厚4mm超):34年
- 鉄筋コンクリート造:47年
一見すると、木造住宅は他の構造よりも耐久性に劣るように感じるかもしれません。法定耐用年数はあくまで法務上の目安で、実際の建物の寿命とは異なります。
出典元:国税庁「法定耐用年数」(https://axf.co.jp/wp-content/uploads/2021/01/AM_03taiyonensu.pdf)
物理的耐用年数
一般的に、耐用年数といえば法定耐用年数のことですが、物理的耐用年数は、建物の物理的・科学的に使用できる期間を示すものです。実際の建物の寿命に近いとされています。
物理的耐用年数は、建物の構造や素材、建築環境、施工業者の技術力など、さまざまな要素から総合的な判断により決定します。そのため、木造住宅といっても一概に年数を言及することはできません。
また、物理的耐用年数はあくまでも目安であり、実際の使用年数はメンテナンスの有無や使用状況によって異なることを理解しておきましょう。
経済的耐用年数
経済的耐用年数とは、その住宅が市場で価値をもち続ける期間を表しています。建物の見た目や機能、メンテナンス状況などが評価に影響し、住宅市場で売買される価値がある期間と考えられるでしょう。
経済的耐用年数は、見た目や間取り、設備の状態、メンテナンスの有無などの要素によって決定されます。さらに、市場の需要にも大きく左右されるため、具体的な年数を一律に示すことは困難です。
なお、日本では木造を含む中古住宅の需要が海外に比べて低いため、経済的耐用年数が短く見積もられる傾向です。
期待耐用年数
期待耐用年数とは、適切なメンテナンスやリフォームを行った場合に、住宅が機能を維持し続けられる期間のことです。実際の年数は、維持管理の状況によって異なります。
期待耐用年数は、日本の中古住宅市場の活性化を目的に導入されたものです。「築20年を超えた住宅は価値がない」といったこれまでの考えを見直すための基準として設定されています。なお、期待耐用年数の正確な算出には、不動産鑑定士や専門家に依頼が必要です。
木造住宅の寿命
前述したように、22年の法定耐用年数はあくまで税務上の指標であり、木造住宅の実際の寿命とは異なります。そのため、木造住宅は20年程度しかもたないと短絡的に判断するのは適切ではありません。
ここからは、木造住宅の一般的な寿命について解説します。日本の木造住宅の平均寿命について見ていきましょう。
平均寿命
早稲田大学の小松幸夫教授らが行った建物の寿命に関する調査によると、木造専用住宅の平均寿命は65年とされています。
これは、建物が建てられてから取り壊されるまでの実際の期間をもとに算出されたものです。法定耐用年数と比べると、はるかに長く住める可能性があることが分かります。
なお、この調査は2011年に実施されたもので、過去にも2回調査が実施されています。1997年の調査結果では木造専用住宅の平均寿命は約44年でした。しかし、2006年の調査では54年、そして2011年の調査では65年とされており、年々木造住宅の平均寿命は延びています。
出典元:早稲田大学教授 小松幸夫「建物の寿命と耐用年数」(https://ykom.w.waseda.jp/KO201603.pdf)
管理次第では80年以上の居住が可能
現在、建築管理の精度や住宅の品質が向上しており、木造住宅の寿命はさらに長くなると考えられています。とくに、日本国内では、環境に優しい住宅の普及が進み、脱炭素対策と連動して補助制度や支援策が充実してきました。
国土交通省が発表した「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」によると、定期的なメンテナンスが定められている長期優良住宅認定の木造住宅では、100年にわたる使用が可能とされています。現代の木造住宅は、管理次第で80年以上快適に住み続けられる住まいといえるのです。
出典元:国土交通省「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新 による価値向上について」(https://www.mlit.go.jp/common/001011879.pdf)
木造住宅の寿命を延ばす方法
木造住宅の寿命を保つためには、日々の暮らし方にも工夫が必要です。住み始めてからは、こまめな掃除や十分な換気など、日常のちょっとした習慣が大切になります。ここでは、木造住宅の寿命を延ばすための具体的な方法について解説します。
こまめな掃除
木造住宅を長持ちさせるには、日常的な掃除が欠かせません。こまめに掃除をすることで、カビの発生や害虫の兆候など、わずかな変化に気づけます。
とくに、結露やシロアリ被害は、見えない場所から進行するため注意が必要です。日々の掃除を通じて異変に早く気づければ、住宅の劣化や損傷を防げるでしょう。
なお、シロアリ点検を定期的に実施する住宅メーカーもあります。住宅を建てる際には、このようなアフターサービスがあるのかを事前にチェックし、活用するのもひとつの方法です。
十分な換気
十分な換気も大切なポイントです。シロアリの発生や木材の腐食は、湿気が大きな原因となります。そのため、注文住宅を建てる際には、効率よく換気ができるよう、窓の位置も考えなければなりません。
風通しをよくするには、東西・南北と、風の通り道を確保し、自然な空気の流れを活かす設計が効果的です。敷地が狭い場合や、周囲に住宅が密集している都市部では、窓の配置や間取りを工夫して、少しでも換気しやすい環境を整えましょう。
木造住宅に長く快適に住み続けるためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。主なメンテナンス内容には、外壁・屋根の塗装や水回りの交換、給排水管の入れ替え、建具の交換などがあります。
築15年ごろには、外壁や屋根の塗装、水回りの設備の交換、築30年を迎えるころには、給排水管の入れ替えやクロス・壁紙の張替え、建具の交換を検討する必要があります。
一般的に、木造住宅のメンテナンスサイクルは、15年ごとが目安とされています。それぞれのタイミングでメンテナンスができるよう、資金計画を立てておくことも重要です。
雨漏り・水漏れの確認
木造住宅の寿命・劣化に大きく影響するのが湿気です。とくに、雨漏りや水漏れによって湿気がたまると、構造部分が腐食し、住宅全体の劣化を早めるおそれがあります。また、湿度が高くなることで、シロアリ発生のリスクも向上します。
こまめな室内外の確認や、定期的に専門業者に点検やメンテナンスを依頼することも、住宅を長持ちさせるために重要です。
木造住宅に用いられる建材の種類
住宅に用いる建材の種類や耐久性についても考慮しなければなりません。建材は、大きく分けて集成材と無垢材の2種類があります。集成材は小角材やひき板を接着剤で貼り合わせた人工的な建材です。
一方、無垢材とは、原木から直接切り出された天然の木材です。ここでは、集成材と無垢材のそれぞれの違いや特性、無垢材の代表的な種類ついて解説します。
集成材
集成材は、小角材やひき板を張り合わせて人工的につくられた木材です。工業製品のため、一定した品質を確保していることが特徴です。強度にばらつきが少なく、比較的安価なことから、構造材をはじめ敷居やドア枠、家具など幅広く活用されています。
用途に合わせて木を選んで加工しているため、幅広く対応できる建材です。その半面、使用された木の種類や接着剤の性能によって強度に差が生じることがあります。
また、集成材は歴史が浅いため、長期的な耐久性はまだ明確なデータが少ないという側面もあります。
無垢材
無垢材とは、天然の木をそのまま切り出して加工した木材のことです。代表的な無垢材には、以下のものがあります。
・スギ
・ヒノキ
・マツ
・ケヤキ
スギは柔らかく安価で加工性に優れているため、床材や梁・柱など幅広く使用されています。ヒノキは耐久性が高く加工性に優れ、高級木材として知られ、床材や柱に多く用いられています。
マツは耐水性が高く、主に使用されるのは梁です。また、ケヤキは強度が高いため、建築材だけでなく家具にも多く使用される木材です。
このほか、クリやヒバなどの無垢材があり、それぞれ特徴と用途があります。建材を選ぶ際は、予算やデザイン、耐久性に応じて適切な樹種を選びましょう。
こちらの記事では、木造と鉄骨の違いについて解説しています。メリットや選び方も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
長く住むためのマイホームづくりのポイントは?
木造住宅に長く住むためには、建築時に使用する木材にこだわり、適切なメンテナンスをするのが大切です。ここでは、長く快適に暮らすためのマイホームづくりのポイントについて詳しく解説します。
長期優良住宅を視野に入れる
長期優良住宅とは、国が定めた建築基準を満たし、長期間にわたって良好な状態で使用できるよう維持保全計画が立てられた住宅のことです。施工時に所管行政庁に申請し、認定を受ける必要がありますが、安心して長く住み続けられる家を実現できます。
さらに、長期優良住宅は、固定資産税や不動産所得税などの税金優遇が受けられるメリットもあります。高い性能を備えている長期優良住宅は、認定時に定めた計画に沿って定期的にメンテナンスをする必要があります。
出典元:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「長期優良住宅認定制度の概要について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001597440.pdf)
気密性能・換気性能を重視する
家の気密性能や換気性能は、長く住み続けるために欠かせない要素です。気密性が高いと室内の温度が安定しやすく、冷暖房の効率が上がるため、光熱費の節約にもつながります。また、結露の発生も抑えやすくなり、建物の劣化防止にも効果的です。
ただし、気密性だけを高めると室内に湿気がこもり、カビの発生や構造部分の腐食を招くおそれがあります。そのため、気密性を高める際には換気性能も重視しなければなりません。
自然換気ではなく、より確実で効率的に換気ができる第一種換気方式の導入を検討するのも方法のひとつです。
将来を見越した間取りを考える
長く住み続けるためには、将来のライフスタイルの変化を見据えた間取りの工夫が欠かせません。子どもの成長や親との同居、在宅ワークなど、家族構成や生活環境の変化に対応できるフレキシブルな間取りを取り入れるのもよいでしょう。
フレキシブルとは、間取りに可変性をもたせることです。近年では、このような柔軟性をもつ「SI住宅」が注目されています。
SIとは、建物の骨組みであるスケルトン(S)と、内装や設備を意味するインフィル(I)を分けて設計する考え方です。SI住宅にすることで、構造を維持しながら内装を自由に変更できるため、世代に合わせてSとIをそれぞれ適切にリフォーム・メンテナンスできるでしょう。
「岡山県の不動産売買情報サイト『岡山で暮らす』」では、オープンハウスや見学会などの住宅イベントを紹介しています。ぜひ、ご覧ください。
断熱性・耐震性にこだわる
家の寿命や安全性を高めるためには、断熱性と耐震性にこだわる必要があります。日本は地震や台風、豪雨など自然災害が多く発生する国です。どれだけ性能が優れていても、断熱性や耐震性が不十分であれば、災害時に大きな被害を受ける可能性があります。
たとえば、断熱性を高めることで、室内の温度を安定でき、結露や湿気による建物の劣化リスクを抑えられます。具体的には、窓や天井、壁に高性能な断熱材を用いる方法が効果的です。
また、耐震性を強化するには、基礎の補強や制振装置を取り入れる方法があります。地震の揺れを軽減する構造を取り入れることで、家族を守る安全な住まいを実現できます。
地盤に関する知識も集める
どれほど耐震性の高い家を建てても、地盤が弱ければ建物への損害リスクからは免れません。地盤が軟弱では不同沈下の問題が起こる可能性があります。ハウスメーカーや工務店を選ぶ際は、地盤調査を適切に実施できる体制が整っているかどうかを見極めましょう。
なお、地盤が強い土地を選ぶことが理想ですが、地盤が弱い場合でも補強工事によって安全性を確保できます。長く安心して住める木造住宅を実現するには、その土地の地盤状況を理解することに加え、必要な補強方法についても知識をもっておくことが大切です。
まとめ
木造住宅の耐用年数は、あくまでも税制上の目安であり、実際の寿命とは異なります。建てた家に長く住み続けるためには、耐久性やメンテナンスといった性能にもこだわる必要があります。
「岡山県の不動産売買情報サイト『岡山で暮らす』」では、岡山県内の不動産会社や工務店・ハウスメーカーの情報を掲載しています。
住宅会社・不動産会社に携わって17年以上の経験があるからこそ、実際に安心してお付き合いができる会社選びを行い、理想の住まいを探すサポートをいたします。
長期優良住宅に対応した住宅会社の情報も紹介しているので、将来を見越した家づくりを検討中の方は、ぜひご活用ください。