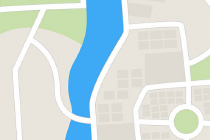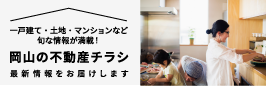家の建てる時期はいつがベスト?かかる費用や頭金についても解説!

家を建てるのにベストな時期はいつでしょうか。住宅購入は大きな買い物のため、購入後に「こうしておけばよかった」と後悔したくはないものです。住宅は購入後に簡単には間取り変更や設備変更などできないため、購入時期を慎重に考える方も多いのではないでしょうか。
家を建てるベストな時期は、家族構成や生活環境、家庭の考えによってさまざまです。しかし、ライフイベントに合わせることで、これからの生活が想像しやすく失敗しにくくなります。
そこで今回は、家の建てるベストな時期を解説します。また、参考にできる世間の家を建てる平均年齢・所得なども紹介します。具体的な家づくりにかかる費用別の特徴や、頭金の貯め方も確認しましょう。
家を建てる時期を決めるための基本情報
世間では、どのようなタイミングで家を建てているのでしょうか。年齢・所得・家族構成の平均をみます。これらの平均は、国土交通省の「令和4年度住宅市場動向調査報告書」を参考にしています。
家を建てる平均年齢
家を建てる時点の平均年齢は注文住宅なら39.5歳、分譲戸建住宅なら37.5歳です。注文住宅か分譲戸建住宅かでは、2歳ほど違いがあります。
2歳の差は、住宅購入費用の違いが原因のひとつです。一般的に、分譲戸建住宅よりも注文住宅の方が高い傾向にあります。頭金など購入資金の準備期間が関係して、比較的購入資金が多く必要な、注文住宅購入の平均年齢が高くなっているのです。
ただし、どちらも30代後半で家を購入しています。ちなみに、初めてのマイホームではなく、建て替えなどで再度購入した場合は、40代後半〜50代後半に購入する方が大半です。
家を建てるための平均所得
初めて家を購入した世帯主の平均所得は、注文住宅で731万円、分譲戸建住宅で722万円です。また、注文住宅の場合の平均所得400万円〜600万円の世帯主は全体の26.3%、400万円未満の世帯主は9%と全体の30%ほどを占めています。
よって、平均所得に満たない世帯でも、実際には購入している家庭が3割程度あるようです。
家族構成と家づくりのタイミング
家を建てる時点での居住人数の平均は、注文住宅は3.2人、分譲戸建住宅は3.5人です。それぞれ最も多い世帯人数は、注文住宅で3人、分譲戸建住宅で4人となっています。一般的な家族構成は、夫婦と子ども1人〜2人です。
どちらの住宅も、子どもがいる家庭が家を建てるケースが多く見られます。
ライフイベントと家づくりのタイミング
上記でも触れたように、家づくりのタイミングは子どもが関係しています。子どもがいる家庭での、一般的なライフイベントは以下のとおりです。ライフイベントごとの家づくりのメリットと合わせて紹介します。
結婚や出産時の家づくり
夫婦のライフイベント計画が明確になっているなら、結婚や出産のタイミングで家づくりを計画するのがおすすめです。住宅ローンを契約する場合、少しでも若い年齢から返済を始める方がよいでしょう。
定年退職後も返済が続くような契約は、できるだけ避けるのがおすすめです。
子どもができる前や出産時のタイミングに家を建てるなら、子どもの人数によって間取りが大きく変わるため、子どもの人数を夫婦でしっかり話し合っておきましょう。仕事部屋や家事部屋を作るのかなど、お互いの考え方も共有しておきましょう。
子どもの入園・入学時の家づくり
子どもの入園・入学のタイミングでの家づくりは、住環境を見直すいいタイミングです。少しずつ親の手が離れ始め、子どもにも自我が芽生え始めます。
また、子ども部屋へのさまざまな希望が出始めたり、これからの生活スタイルも見え始めたりするため、間取りを決めるのに最適な時期です。
子どもの通学を考慮して、家づくりは立地にも気を配りましょう。通う学校が決まっているタイミングであれば、通学路は安全か、遠すぎないかなどの確認もできます。
引っ越しのタイミングは入園・入学前がおすすめです。まずは先に引っ越して住環境に慣れましょう。その後の慣れたタイミングで新しい環境での通学を始めると、子どものメンタル面の負担を減らせます。
子どもの独立時の家づくり
これからの老後の生活を踏まえて、子どもの独立時に家づくりを計画するのもよいでしょう。このタイミングであれば、家の大きさや間取りを最小限にできるため、建築費用を抑えられます。
また、2人だけの利便性を考えて間取りを決められるため、バリアフリー設備を整えたり掃除しやすいコンパクトな間取りにしたりなどの工夫もしやすいでしょう。ただし、いずれ子ども達が結婚し、孫を連れてきてもゆったりと過ごせるよう、来客スペースなどの確保は忘れずに計画しましょう。
昇給や昇格のタイミング
昇給や昇格のタイミングで家づくりを計画するのもおすすめです。
収入が増えたり役職がついたりすると、住宅ローン審査に通りやすくなります。一度結婚などのタイミングで住宅ローン審査をして思うような結果が出なかった場合、昇給や昇格のタイミングまで待つのもひとつの方法です。
借入額を減額して妥協したマイホームを建てるよりも、昇給や昇格を待って理想の家づくりをする方が、満足度の高い生活を送れます。ただし、無理な返済計画を立てないように予算のシミュレーションはしっかり行いましょう。
家づくりにかかる費用
では、家づくりにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。広い家に住み替えた場合の費用や予算別の住宅の特徴を紹介します。
家賃と住宅ローンの比較
家賃の支払いと住宅ローンの返済は、支払額が同じであっても意味合いが異なります。家賃とは住宅の貸主に支払う使用料です。住宅は貸主のもので、長期的に払い続けても自分のものになることはありません。
一方、住宅ローンは金融機関から借りる住宅費用です。住宅ローンを完済すれば、住宅は自分の資産となります。賃貸は後に何も残りませんが、住宅購入は資産運用の一種として残ると捉えることも可能です。
また、住宅ローンは保険としての役割もあります。住宅ローンを契約する場合は、団体信用生命保険への加入が必要です。団体信用生命保険に加入していれば、借主が死亡もしくは所定の高度障害状態になった場合に、保険会社が借主の代わりとなって住宅ローンの残高相当額を支払ってくれます。
このように、借主にもしもの事態が起こっても、家族は今後の住宅ローンを支払わずに、引き続き住み続けることが可能になるのです。賃貸では得られないもしものときの安心を、住宅購入なら得られます。
広い家への住み替え
広い家に住み替える場合は、初めて家を購入する以上の費用がかかります。新居の購入費に加えて、
- 現在の家の売却にかかる費用
- 仮住まい費用
- 新居の諸費用
などが必要です。現在の家の売却には、売却に必要な諸費用や住宅ローン残高を完済するための費用がかかります。
売却した費用を新居の費用にあてればいいと考えがちですが、購入費以外にもさまざまな費用が追加でかかるため、注意しましょう。また、広い家への住み替えなら新居の購入費用自体も高額になります。
予算別にみた住宅
1,000万円台から4,000万円台、予算別の住宅の特徴を紹介します。ただし、予算には土地代は含まれていません。
1,000万円台の住宅
予算1,000万台の住宅は、コスト重視で性能や広さなどを極力抑えた家づくりになります。予算を抑えるためには、以下をポイントにコストを削減しましょう。
- 低予算でも受けてくれるハウスメーカーを探す
- 建物はシンプルな設計にする
- 延べ床面積を35坪以下にする
- 窓を小さくする
- 設備を最低限にする
たとえ低予算の住宅であっても、安全面を考慮する必要があります。最低限のセキュリティや基礎など、しっかり確保した上で家づくりをしましょう。
2,000万円台の住宅
予算2,000万円台の住宅は、買主の希望をある程度取り入れられる家づくりです。延べ床面積は35坪以上で建てられたり、大手のハウスメーカーに依頼できたりするなどの余裕も生まれます。
ただし、設備のグレードを上げたり素材にこだわったりすると、予算を超えてしまう可能性があるため気をつけましょう。希望の優先順位を決めて予算組みするのがおすすめです。
3,000万円台の住宅
予算3,000万円台は、2,000万円台の内容に加えて、間取りや内装にもこだわれます。延床面積の余裕がさらに生まれるため、部屋数を増やすことも可能です。ある程度グレードを上げても予算内に収めることもできますが、オプションを採用しすぎるとオーバーすることもあります。
4,000万円台の住宅
予算4,000万円台なら、多くのこだわりを家づくりに十分反映できます。中庭を作ったり二世帯住宅を建てたりすることも可能です。多くの最新設備を取り入れたり使用する素材にこだわったりしたとしても、おおよそ予算内に抑えられるでしょう。
頭金を貯めてマイホームを持とう
住宅ローンを契約するために頭金は必須ではありません。契約したい金額や金融会社など、条件によっては頭金なしでも住宅ローンは組めます。しかし、住宅は頭金を貯めてから購入しましょう。
頭金の重要性
頭金ありの場合となしの場合では、同じ金額の住宅でも住宅ローンを契約する金額が異なります。月々の返済額や返済期間がかわり、返済期間が長い方が総住居費が多くなるでしょう。これは、返済期間が長くなると利息が増えるためです。
また、ローン完済年齢も上がるため、返済開始年齢によっては退職後も支払いが続く場合もあります。
頭金の目安
頭金の目安は、支払総額の2割程度が適しています。2,000万円の住宅ローンを契約するなら400万円、4,000万円なら800万円です。
しかし、月々の支払い可能額は家庭によって異なります。住宅ローンを組む前にシミュレーションして、無理なく支払える金額を目安として頭金を用意するとよいでしょう。
低金利の影響
住宅ローンを契約すると、返済時は元金とともに利息を支払います。この利息は金利によって変わるため、金利が低い時期に家を建てると、頭金や総費用を抑えることが可能です。
住宅ローンを契約するなら、金利が低いタイミングで契約しましょう。ただし、現代は低金利時代です。今後金利がほとんど変動しない、もしくは金利が上がるようであれば、頭金を貯蓄するよりも、早期に頭金なしで住宅ローンを組んで繰り上げ返済する方が有利になることもあります。
また、金融機関によっては、頭金ありの場合に金利を優遇してくれることがあります。住宅ローン契約予定の金融機関に金利優遇プランがある場合は、頭金を入れる方がお得です。
頭金を貯めるための計画
頭金は無理なく計画的に貯めましょう。頭金を貯めるための方法を紹介します。
財形貯蓄
財形貯蓄はいくつかあります。そのうちのひとつ勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)とは、毎月もしくはボーナス時期に勤め先から支払われる賃金からの控除(天引き)により、事業者を通じて積み立てていく貯蓄のことです。
目的を問わない制度のため、頭金のための貯蓄にも利用できます。
年齢制限もなく、複数契約できる便利な制度ですが、3年以上の積み立てが条件です。3年以上にわたって頭金を貯める計画を立てている方におすすめします。
また、財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる財形持ち家転貸融資の条件を満たせば、長期で低利の融資を利用することも可能です。
株や外貨への投資
現在ある資金を、株や外貨へ投資して資金を増やす方法もあります。しかし、投資は必ず増える保証はなく、資金が減るリスクも伴うため注意が必要です。事前にしっかり知識を入れて、自分にとって投資するメリットを確認してから行いましょう。
コツコツ貯金
頭金を貯める期間を多く取れるなら、地道にコツコツ貯金するのも有効な手段です。長期的に行う必要はありますが、リスクはなく定期的な貯金を継続すれば、必ず頭金を用意できます。
ただし、少額ずつの貯金であれば、かなりの期間が必要です。住宅購入希望時期から逆算し、いつから始めれば予定時期に貯まるかをしっかりシミュレーションしましょう。
相続時精算課税制度
親から頭金を援助してもらうのもひとつの方法です。親から援助を受けるなら、相続時精算課税制度を理解しておきましょう。
相続時精算課税制度とは60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に対して、2,500万円までの財産を贈与する場合に、贈与税が非課税になる制度です。2,500万円以上の援助を受けると贈与税がかかる点に気をつけましょう。