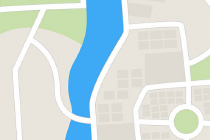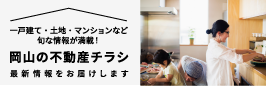長期優良住宅とは?新築で受けられる補助金について解説!

省エネ性能と耐震性に優れた長期優良住宅は、地震や台風などの災害にも強く、長期的な視点に立った設計により住み心地のよさも追求されています。断熱性能や設備機器の省エネ性能も高く、光熱費を抑えることも可能です。
そして、補助金や税金の免除にも強い住宅として知られています。
本記事では長期優良住宅の特徴や、新築で受けられる補助金の種類と申請方法を分かりやすく解説します。長期優良住宅についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
長期優良住宅とは?
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅です。国土交通省が定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、認定制度が設けられています。
長期優良住宅の認定基準や災害・居住考慮の基準などを、これから詳しく解説します。
長期優良住宅の認定基準
長期にわたって良好な状態を維持できるよう、長期優良住宅は一定の基準を満たす必要があります。長期優良住宅に認定される基準は、以下の5つです。
- 長期に使用するための構造及び設備を有していること
- 居住環境等への配慮を行っていること
- 自然災害等への配慮を行っていること
- 一定面積以上の住戸面積を有していること
- 維持保全の期間、方法を定めていること
どれかひとつが欠けていれば、長期優良住宅には認定されません。すべての条件を備えている家のみが認定されるため、住宅を建てる際には条件をしっかりチェックする必要があります。
また、認定を受けた方を対象に調査を行うことがあります。その際は、建築・メンテナンスの状況に関する記録などを活用して報告を行いましょう。
計画に基づいて建築やメンテナンスをおこなわない場合、認定をした所管行政庁から改善を指示されることがあります。それに従わない場合、認定が取り消される可能性があるため、注意が必要です。
岡山県が定める認定基準
岡山県の認定基準およびその他の必要な事項は、岡山県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱によって定められています。(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市を除く)
以下の認定基準を定めており、内容は以下のとおりです。
居住環境基準(法第6条第1項第三号関係)
居住環境基準は、長期優良住宅が良好な景観の形成や、地域における居住環境の維持及び向上に配慮することを求めるものです。各所管行政庁が具体的な要件を選定して公表することになっています。
岡山県で長期優良住宅を建てる際は、以下の計画に該当するかチェックしておきましょう。
下記の地区計画に該当する場合、建築物の敷地、構造、建築設備、用途、デザインなどに関する規定を守る必要があります。この計画に適合しない場合は認定ができません。以下の地区計画にかかる場合は、各市が発行する適合通知書を添付する必要があります。
- 赤磐市:赤磐市桜が丘東地区地区計画・赤磐市桜が丘西地区地区計画・あかいわ山陽総合流通センター地区計画
- 浅口市:占見新田地区計画・フルライフガーデン鴨方地区地区計画・佐方ニュータウン地区地区計画 ・竹原地区地区計画
- 高梁市:奥万田地区地区計画
下記の景観計画の対象地域にある住宅の場合、建築物の敷地、構造、建築設備、用途、デザインなどに関する規定を守る必要があります。この計画に適合しない場合は認定ができません。以下の景観計画にかかる場合は、行政庁が発行する適合通知書を添付する必要があります。
- 岡山県景観計画
- 瀬戸内市景観計画
- 早島町景観計画
- 真庭市景観計画
- 高梁市景観計画
- 奈義町景観計画
下記の区域内にある場合、原則として認定はできません。ただし、長期間の立地が確認されている場合は認定が可能な場合があります。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良区域
申請予定の建築物が該当するかどうかは、各市町村に問い合わせましょう。
災害配慮基準(法第6条第1項第四号関係)
災害配慮基準は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、国土交通省が定めた基準です。土砂災害、津波、洪水などの自然災害による被害の防止、又は軽減することを目的としています。
この基準は、災害リスクの高い地域における住宅の耐災害性を高めることで、住民の安全と安心を確保するために重要な役割を果たしています。
下記の区域内では、長期優良住宅の認定ができないため、注意しましょう。
- 土砂災害特別警戒区域:土砂崩れが発生する可能性が高い地域。
- 地すべり防止区域:急傾斜地の崩壊による危険性がある地域。
- 急傾斜地崩壊危険区域:地滑りの危険性がある地域。
- 災害危険区域:津波、高潮、出水等による危険の著しい地域。
- 津波災害特別警戒区域:津波による浸水被害の可能性がある地域。
- 浸水被害防止区域:洪水や出水などの水害による浸水リスクが高い地域。
岡山県では、以下のサイトから各区域の指定場所を確認できます。現在、岡山県内では災害危険区域、津波災害特別警戒区域、及び浸水被害防止区域の指定はありません。
土砂災害特別警戒区域は、 おかやま全県統合型GISで確認できます。必ずGIS内に掲載されている公示図書を参照してください。
地すべり防止区域は、 国土交通省(岡山県 防災砂防課)、農林水産省農村振興局(岡山県 耕地課)、林野庁(岡山県 治山課)がそれぞれ定めています。詳細確認が必要な場合は、建物の位置が分かる図と地番を準備し、担当の課や地域事務所に問い合わせましょう。
急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地崩壊危険区域一覧(岡山県 防災砂防課)で確認できます。詳細確認が必要な場合は、建物の位置が分かる図と地番を準備し、担当の課や地域事務所に問い合わせましょう。
長期優良住宅のメリットは?
省エネルギー性能やバリアフリー面におけるメリットが大きく、地震などにも強いため安全性と快適性に優れているのが特徴です。しかし、それ以外のメリットも存在します。長期優良住宅の主なメリットは、以下の5つです。
- 税制の控除・減税を利用できる
- 住宅ローンの金利が優遇される
- 地震保険料の割引が受けられる
- 補助金を受けられる場合がある
- 資産価値が高い
各項目を以下で詳しく解説します。
税制の控除・減税を利用できる
長期優良住宅は、税制の控除・減税を受けられます。対象となる税金は、以下の6つです。
- 不動産取得税
- 住宅ローン控除
- 登録免許税
- 投資型減税
- 固定資産税
- 贈与税
各税金面におけるメリットをこれから詳しく解説するので、ぜひご覧ください。
不動産取得税
不動産を購入したときには、不動産取得税という税金がかかります。長期優良住宅を購入した場合、不動産取得税の控除額が異なります。計算方法は以下のとおりです。
一般住宅の場合:不動産取得税(建物)=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
長期優良住宅の場合:不動産取得税(建物)=(固定資産税評価額-1,300万円)×3%
一般的な住宅に適用される不動産取得税の控除額は、1,200万円となっています。しかし、長期優良住宅は、この控除額が100万円高い1,300万円です。
数万円の差ですが、長期優良住宅にすることで減税を受けられます。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を、最大13年間にわたり所得税から控除できる制度です。また、所得税から控除できなかった分は、翌年の住民税から控除されることになります。
適用ローンの最大金額は、一般住宅では3,000万円ですが、長期優良住宅では4,500万円です。
一般住宅の場合、年間の控除額上限が21万円です。しかし、長期優良住宅を建てると31.5万円に年間控除額上限がアップします。長期優良住宅は一般住宅より、年間で10.5万円の節税効果を期待可能です。
また、長期優良住宅で住宅ローン控除を受けるための条件があるため、国税庁のホームページを確認してください。
適用条件や申請方法は複雑ですが、正しく申請することで、毎年税金が戻ってきます。ぜひ住宅ローン控除を活用し、お得に長期優良住宅を手に入れましょう。
登録免許税
不動産を購入すると、所有権登記にも税金がかかります。それが、登録免許税です。
長期優良住宅を購入することで、一般住宅に比べて所有権登記の税率が低くなります。保存登記は一般住宅の場合0.15%、長期優良住宅の場合0.1%です。移転登記は一般住宅の場合0.3%、長期優良住宅の場合0.2%になります。
たとえば、住宅の評価額を4,000万円と仮定して計算してみましょう。一般住宅の場合、保存登記に6万円、移転登記に12万円、合計で18万円かかります。
一方、長期優良住宅では税率が低いため、保存登記は4万円、移転登記は8万円で、合計12万円です。これにより、6万円の節税効果があります。
投資型減税
投資型減税とは、長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅の新築住宅を、ローンを利用せずに自己資金のみで購入した際に利用できる制度です。
長期優良住宅や認定低炭素住宅を建てる際の性能強化に必要となった費用が対象となります。このような費用を「掛かり増し費用」と言います。
掛かり増し費用から10%の金額を計算し、所得税から控除できます。控除限度額は650万円であるため、最大で65万円を所得税から控除できます。
住宅ローンの控除と異なるのは、減税の回数です。投資型減税による控除は、1回しか利用できません。
固定資産税
不動産は所有しているだけで毎年固定資産税がかかります。新築住宅は3年の間、固定資産税が半分に免税されるのがメリットです。新築の長期優良住宅を建てた場合、この軽減期間が5年になるためさらにお得です。
新築住宅購入時の固定資産税は以下の方法で計算できます。
固定資産税(建物):評価額×1.4%×1/2
また、評価額は毎年価値が下がりますが、5年の間、毎年納めなければならない固定資産税を安くできるのは非常に大きなメリットといえるでしょう。
贈与税
住宅の購入資金を親から援助してもらうと、一定額が非課税となることはあまり知られていません。
一般的な住宅の場合、非課税となる金額は500万円です。しかし、省エネ住宅に該当する長期優良住宅を購入すると、贈与税の非課税金額は1,000万円まで アップします。非常に高額な税金の節約効果が期待できるため、親族からお金を借りて長期優良住宅を建てるのはお得だといえるでしょう。
住宅ローンの金利が優遇される
長期優良住宅は、フラット35の金利における優遇が受けられるのも特徴です。
フラット35では、金利を引き下げる〔フラット35〕Sという商品を利用できます。〔フラット35〕Sは、省エネ性能や耐震性などに優れた質の高い住宅を取得する場合に、一定期間金利が引き下げられるのが特徴です。
長期優良住宅の場合、借入をしたときから5年間、金利を0.25%下げられます。
長期優良住宅の新築で負担を減らしたい方は、活用してみてください。
地震保険料の割引が受けられる
地震保険に関する割引を受けられるのも、長期優良住宅のメリットです。耐震等級が高い物件は、保険料の割引率が高くなります。
長期優良住宅は一般的に耐震等級が2以上でなければなりません。 一般的な耐震等級1の建物は、保険料の割引率が10%と定められています。耐震等級が2 になると割引率は30%まで一気に高まるため、大幅な保険料の節約効果が期待できます。
なお、 にまでアップ可能です。耐震等級を証明する書類を地震保険の会社に提出し、ぜひ割引を受けてください。
補助金を受けられる場合がある
長期優良住宅は、購入・建築するとさまざまな補助金を受けられる可能性があります。代表的な補助金の例は、エコやグリーン化事業に関するものです。
多くの場合、地域に根差した木材などで建てられた住宅であることや、特定の世代であることが条件となります。国や自治体のホームページから問い合わせてください。
快適に長期間住める
省エネで建物自体が傷みにくいのも、長期優良住宅のメリットです。
環境に考慮して作られているということは、夏の暑さや冬の寒さに住宅が強いことの証明にもなります。これから日本の気候はいっそう暑くなり、従来の住宅では傷みやすくなってくる可能性は否めません。
断熱材を使っていない住宅では、気温差に関する問題も生じやすいでしょう。
長期優良住宅は温度や湿度の調整もしやすく、快適な空間で生活可能です。家そのものの寿命も快適性も高くなり、子どもやお年寄りも暮らしやすい家といえます。次の世代にも家を残したいと考えている方や、家族の健康を守りたい方に長期優良住宅はおすすめです。
資産価値が維持しやすい
長期優良住宅は住宅そのものが傷みにくいため、資産価値を維持できます。住宅の定期的なメンテナンスをすれば、資産としての家の価値を維持できます。将来家を売るときの売却価格も、高く設定できるでしょう。
一般的な住宅は、メンテナンスが予定に組まれないため状態不良が進みがちです。しかし、長期優良住宅はメンテナンスがハウスメーカーの予定に組まれているため、住宅の価値を維持しやすくなります。
断熱・耐震性が高められているため、住宅の寿命も長めです。
長期優良住宅のデメリットは?
一見メリットが大きいように見える長期優良住宅ですが、以下のようなデメリットも存在します。
- 費用や時間がかかる
- 仕様変更により建築コストが増加する場合がある
- 定期的なメンテナンスや維持費が発生する
デメリットを事前にチェックし、自分に長期優良住宅が向いているかを正しく見極めましょう。
費用や時間がかかる
長期優良住宅の認定を受けるためには、建築前に手続きをするため、申請費用と時間がかかります。
事前準備には1か月程度を要するケースが多いです。建てる前に基準に合うかチェックされる長期優良住宅の性質上、これは避けられない問題といえます。
長期優良住宅を建てるなら一般的な戸建てよりも予算を多めに用意し、余裕を持った建築計画を立てることが大切です。数多くの長期優良住宅を手がけているハウスメーカーを選べば、手続きがよりスムーズに進むでしょう。
仕様変更により建築コストが増加する場合がある
長期優良住宅の仕様に変更をすると、コストそのものが非常にかかるのもデメリットです。コストを抑えられるハウスメーカーの住宅を選んだとしても、長期優良住宅の条件を満たすためのアップグレード費用が必要な可能性が出てきます。
とくに梁や柱の追加で耐震性を高めたり、サッシや窓ガラスを断熱性の高いものにしたりするための費用はかかりやすいです。住宅の仕様に太陽光発電などの設備がない場合には、それらを追加する必要も出てくるでしょう。
住宅の総コストがかかることを理解し、長期優良住宅の建築をするかは決めてください。
標準の性能で基準を満たす建築会社もある
長期優良住宅を建てるときにコストが上がるのを避けるために、標準性能で基準を満たしている建築会社を選ぶこともできます。複数の建築会社に長期優良住宅を建てたいことを伝え、住宅に関するプランニングをしてもらってください。
太陽光発電や断熱、耐震性などに特化した住宅が標準で、性能について基準を満たしており、追加費用が発生しにくく予算を抑えられます。
具体的な仕様の確認が必要
住宅の仕様をしっかり確認し、長期優良住宅にできるかは必ずチェックしてください。とくに断熱性能や耐震性能は、チェックすべきポイントです。標準仕様のままで条件を満たすところもあれば、アップグレードが必要なところもあります。
費用をできるだけ節約するなら、アップグレードを極力少なくして住宅を建てましょう。
建築会社によっては、長期優良住宅相当の家を提供しているところもあります。相当や仕様などの言葉が付けられている住宅は、同程度の性能を維持しているだけで認定を受けられない可能性も否めません。
新築を相談をする際には、必ず長期優良住宅に「認定」できる家かをチェックしましょう。
景観を守らなければ長期優良住宅に認定されない場合には、住宅の外観を変えられるかも重要です。標準仕様の規格住宅の場合、外観を変えられない可能性もあります。予算が潤沢にある場合には、必要に応じ注文住宅も検討してください。
定期的なメンテナンスや維持費が発生する
長期優良住宅は非常に高度な設備を使用しているため、定期的なメンテナンスも必要となります。管理に関しても評価基準が義務付けられているため、メンテナンスを怠ることはできません。
以下のようなメンテナンスをしないままでいると住宅の性能が落ち、長期優良住宅の認定から外されるリスクがあります。
- 30年以上の点検メンテナンス、点検の間隔は10年以内
- 規模が大きい地震や台風の際の臨時点検
- 不備が出た箇所の修繕や調査・改良
- 定期的な維持保全計画の見直し
チェックは抜き打ちのため、普段からしっかりメンテナンスをしていないと資格を剥奪されるリスクもあります。
メンテナンスの費用を抑えるためには、長期優良住宅を得意とするハウスメーカーで家を建てるのがおすすめです。家を建てるだけでなく、メンテナンスに関するプランニングもしてもらえます。
多くの建築会社では定期点検が用意されている
多くの建築会社では長期優良住宅を建てれば、定期点検やメンテナンスを行ってくれます。ハウスメーカーが用意した点検プランをきっちり行えば、長期優良住宅を維持できる可能性は非常に高いです。
自分で定期点検の計画を立てるのは、長期優良住宅に住む方にとって難しいものです。適切なハウスメーカーを選び、計画的な点検をしてもらって確実に住宅の価値を維持することをおススメします。
リフォーム・増築には計画変更の提出が必要になる
長期優良住宅に対し、リフォームや増築を行う際には新築時と同様に申請が必要です。リフォーム・増築した部分に関しても長期優良住宅の基準を満たす必要があります。
小規模なリフォームの場合には、申請なしで問題がない可能性もあります。ただし、リフォーム工事の契約書や図面などは、メンテナンス記録として保存しないといけなかったりするので、リフォームの前には自治体に相談をする必要があるでしょう。
新築時に受けられる補助金は?
長期優良住宅の新築時に受けられる主な補助金は、以下の2種類です。
- 地域型グリーン化事業
- 子育てエコホーム支援事業
長期優良住宅の新築を検討している方は、ぜひこれらの補助金制度を活用し、お得に高性能住宅を手に入れましょう。各補助金の金額や対象、特徴などをこれから詳しく解説します。
地域型グリーン化事業
2015年から2023年まで実施されていた「地域型住宅グリーン化事業」は、長期優良住宅にも適用される補助金です。今回は、制度が再開された際スムーズな申し込みに役立てられるよう、2023年までにおける本事業の概要を紹介します。
2024年7月現在は公募がなく、今後の実施は未定となっています。しかし、 には組み込まれており再開の可能性もあるため、引き続き最新の情報をチェックすることが大切です。
地域型グリーン化事業では、地域の木造住宅関連事業者がグループを結成し、省エネルギー性能や耐久性に優れた木造住宅の整備とあわせて、三世代同居への対応などを支援していました。
地域の工務店などで建築した対象住宅は、この事業の補助金を受けられていました。公募によって国土交通省から採択を受けた認定業者への施工依頼でのみ、この制度が活用できた点も大きな特徴です。
住宅の要件
2023年に実施された地域グリーン化事業では、長寿命型(長期優良住宅)またはゼロ・エネルギー住宅型(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Oriented、認定低炭素住宅)が補助の対象となっていました。
また、以下の要件を遵守する必要がありました。ここでは、主な項目のみをわかりやすくピックアップしています。
| 住宅に対する要項 |
|
| 施工事業者に対する要項 |
|
補助金額
補助金額は「こどもエコ活用タイプ」と「通常タイプ」どちらの制度を使用するか、また、長寿命型やゼロ・エネルギー住宅型など住宅タイプによって細かく分けられていました。
こどもエコ活用タイプとは、後述する「こどもエコすまい支援事業」の補助金を活用しながら、地域型グリーン化事業の条件を満たすことにより補助金を上乗せする制度です。
加算措置と制度別・住宅タイプ別の補助額は、表のとおりです。以下の加算条件と照らし合わせてご覧ください。また、条件①と②は併用できません。
【加算措置】
①地域材加算(すべて)
②地域材加算(過半)
③三世代同居加算
④地域住文化加算
⑤バリアフリー加算
【こどもエコ活用タイプ】
| 区分(住宅の性能) | 活用実績 | 加算措置を2つ以上利用 | ①③⑤のいずれかの加算措置利用 | ②④のいずれかの加算措置利用 | 加算利用無し |
| 長寿命型 (認定長期優良住宅 | 未経験枠 | 135 万円 | 125 万円 | 115 万円 | ※制度併用なし |
| 制限なし枠 | 125 万円 | 115 万円 | 105 万円 | ||
| ゼロ・エネルギー住宅型・ 長期対応(ZEH、Nearly ZEH) | 未経験枠 | 140 万円 | 130 万円 | 120 万円 | |
| 制限なし枠 | 130 万円 | 120 万円 | 110 万円 | ||
| ゼロ・エネルギー住宅型・ ZEH(ZEH、Nearly ZEH) | 未経験枠 | 135 万円 | 125 万円 | 115 万円 | |
| 制限なし枠 | 125 万円 | 115 万円 | 105 万円 | ||
| ゼロ・エネルギー住宅型・ 低炭素(ZEH Oriented、 認定低炭素住宅) | 未経験枠 | 110 万円 | ※制度併用なし | ※制度併用なし | |
| 制限なし枠 | ※制度併用なし |
【通常タイプ】
| 区分 (住宅の性能) | 活用実績 | 加算措置を2つ以上利用 | ①③⑤のいずれかの加算措置利用 | ②④のいずれかの加算措置利用 | 加算利用無し |
| 長寿命型 (認定長期優良住宅) | 未経験枠 | 105 万円 | 95 万円 | 85 万円 | 70 万円 |
| 制限なし枠 | 95 万円 | 85 万円 | 75 万円 | ||
| ゼロ・エネルギー住宅型・ 長期対応(ZEH、Nearly ZEH) | 未経験枠 | 110 万円 | 100 万円 | 90 万円 | |
| 制限なし枠 | 100 万円 | 90 万円 | 80 万円 | ||
| ゼロ・エネルギー住宅型・ ZEH(ZEH、Nearly ZEH) | 未経験枠 | 105 万円 | 95 万円 | 85 万円 | |
| 制限なし枠 | 95 万円 | 85 万円 | 75 万円 | ||
| ゼロ・エネルギー住宅型・ 低炭素(ZEH Oriented、 認定低炭素住宅) | 未経験枠 | 80 万円 | 70 万円 | 70 万円 | |
| 制限なし枠 | 70 万円 | 70 万円 | 70 万円 |
子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業は、環境に配慮した快適な家を作ることを目的とし、子育て世帯・若者夫婦世帯を支援するための補助金制度です。2050年カーボンニュートラルの実現を目標としています。
大好評だった「こどもエコすまい支援事業 」の後継事業として、2024年度よりスタートしました。こどもエコすまい支援事業は予算上限により、令和5年9月28日時点で終了しました。
対象やこどもエコすまい支援事業との違い、申請期間などをこれから詳しく解説します。
こどもエコすまい支援事業との違い
2023年まで実施されていた「こどもエコすまい支援事業」と「子育てエコホーム支援事業」の違いは、対象住宅の種類と建築や購入時、リフォーム時の補助金です。
こどもエコすまい支援事業は、長期優良住宅、ZEH住宅、それ以上のZEHレベルを満たす住宅が対象で、建築や購入時の補助金は一律100万円でした。一方、子育てエコホーム支援事業は、ZEH住宅に対する補助金は80万円になりました。
また、リフォーム時の補助金 が以前は30〜60万でしたが、20〜60万円に変更され、最低補助額が引き下げられました。
長期優良住宅の変更はないため、引き続き従来の基準を満たす住宅が補助対象となります。
対象と補助金額
対象となるのは、子育て世帯や若者夫婦世帯です。新築住宅の取得と住宅のリフォームの両方が対象となります。リフォームは、子育て世帯や若者夫婦世帯ではなくても活用可能です。
新築する際には、長期優良住宅またはZEH住宅であることを証明する書類が必要であり、次の条件を満たす必要があります。
- 所有者が自ら居住すること
- 床面積が50~240㎡であること
- 土砂災害特別警戒区域または災害危険区域に該当しないこと
- 都市再生特別措置法第88条第5項の規定による勧告に従わなかった事実が公表されていないこ
- 交付申請時に一定基準の工事が完了していること
これらの条件を満たすことで、長期優良住宅は1住戸あたり最大100万円、ZEH住宅は1住戸あたり最大80万円の補助制度を利用できます。事前に詳細な条件を確認し、計画的に進めることが大切です。
リフォームの 、その他の世帯は30万円です。リフォームの場合、以下の項目に対し補助金が支給されます。
- エコ住宅設備の設置工事
- 外壁や屋根、天井、床などの断熱改修工事
- 開口部に断熱をする改修工事
- バリアフリー改修工事
- 子育て対応の改修工事
- 防災性を高める改修工事
- 空気清浄機能を高めたり換気機能のあるエアコンを設置したりする工事
- リフォーム瑕疵に関する保険加入
以上の工事を行い、 を超えれば、補助対象となります。しかし、必須条件や組み合わせでのみ適用される条件もあるため、注意しましょう。
申請期間
申請期間は2024年3月29日〜2024年12月31日です。工事を始める前に工事請負契約書の締結が必要で、2024年12月31日までに基礎工事が完了していることも求められるため、十分に注意しましょう。
また、交付申請の受付は2024年12月31日までとされていますが、予算が上限に達すると終了してしまうため、早めの対応をおすすめします。
子育てエコホーム支援事業を利用するときの注意点
子育てエコホーム支援事業で注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入を検討している場合、いくつかの内容に注意が必要です。
市街化調整区域や土砂災害警戒区域、浸水想定区域に家を建てる場合、補助金が半額になります。長期優良住宅の場合、補助金は50万円に減ります。土地を購入する前に、減額の対象となる区域に入っていないか確認しましょう。
また、子育てエコホーム支援事業は、原則として国が行っている以下のような補助制度とは併用できません。
- 地域型住宅グリーン化事業
- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業
- 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業
- 集合住宅の省CO2化促進事業
判断が難しい場合は、補助金の事務局に問い合わせて確認しましょう。
こちらの記事では、岡山県に移住するときに使える補助金・支援金について解説しています。市ごとに分けて取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
まとめ
長期優良住宅は、住みやすさはもちろん、補助金や光熱費の節約ができる住宅です。耐震性や耐久性、省エネ性、バリアフリーなどに優れており、高性能な家として知られています。住み心地のよさはもちろん、資産価値の向上にもつながる魅力的な住まいです。
しかし、長期優良住宅は、建築期間が長くなったり、特定の要件を満たす必要があったりします。メリットとデメリットを理解しながら、長期優良住宅を建てるかどうかを検討しましょう。
岡山で長期優良住宅を検討している方は「岡山県の不動産売買情報サイト『岡山で暮らす』」をご利用ください。長期優良住宅に対応できる工務店・ハウスメーカーの情報を提供しています。
オープンハウス・完成見学会・モデルハウスなどのイベント情報も掲載されているため、お気軽にお問い合わせください。