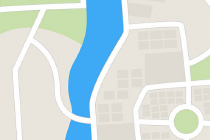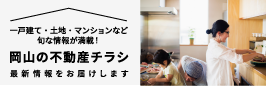二世帯住宅の相場ってどれくらい?土地あり・土地なしでの価格を比較!

現在は賃貸物件で暮らしているものの、将来的には自分の家を持ちたいと考えている人は多いでしょう。なかには、両親とも暮らせる二世帯住宅を検討する人も少なくありません。
この記事では、二世帯住宅を建てる際にかかる費用相場を土地のありなし、二世帯住宅の種類ごとに詳しく解説しています。費用を抑える方法やコスト削減のために利用できる制度についても紹介しますので、参考にしてください。
目次
二世帯住宅の相場とは
まずは、以下の種類ごとに相場を解説します。
- 完全分離型の場合
- 一部共有型の場合
- 完全共有型の場合
種類ごとの特徴も簡単に紹介しますので、相場とあわせて確認しましょう。
完全分離型の場合
完全分離型は、親世帯と子世帯がひとつの建物内に住みながらも、生活空間を完全に独立させた間取りです。設備やスペースが二世帯分必要なため、建築費は一般的に高額となりやすく、3,000万~5,400万円程度が相場です。
完全分離型では玄関からキッチン、リビング、浴室、トイレに至るまで、すべての設備を世帯ごとに設けるため、互いのプライバシーを守れます。間取りの工夫によって、生活音や生活リズムの違いによるストレスを軽減できるのが特徴です。
たとえば、1階を親世帯、2階を子世帯の居住スペースに分ける「上下分離型」や、左右に区切る「左右分離型」など、家族構成や希望に応じて柔軟な設計が可能です。加えて、将来的に子世帯のみが住む場合でも、賃貸物件として活用できます。
建築費は高めですが、家計の管理が分けやすく、設備の使用時間を気にする必要がありません。世帯間で生活リズムがまったく異なる場合や、互いのプライバシーを守りたい場合におすすめです。
こちらの記事では、二世帯住宅の完全分離型についてくわしく解説しています。メリット・デメリットや注意点についても取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
一部共有型の場合
一部共有型は、二世帯住宅のなかでも適度な距離感を保ちながら生活できるスタイルです。設備の一部を共有するため、完全分離型と比較すると費用は抑えやすく、2,400~4,500万円程度が目安となります。
一部共有型でよくみられるのが、「玄関だけ」、「リビングだけ」、「水回りだけ」などを共有し、その他の設備は世帯ごとに分ける方法です。共有する部分ができるので、「完全分離型」よりも費用を抑えることができます。
ただし、設備を共有することで発生する家事の役割分担や生活費の負担割合は、事前にしっかり話し合っておく必要があります。たとえば、風呂の掃除や食事の時間、入浴の順番など、共有スペースがある分だけコミュニケーションを図りましょう。
完全共有型の場合
完全共有型は、親世帯と子世帯が設備や空間をすべて共有するスタイルの二世帯住宅です。費用の相場は1,800万~3,600万円程度で、二世帯住宅のなかでは最もコストを抑えやすいタイプです。
コストを抑えやすいのは、すべての設備や空間を共有するためです。光熱費や家電の購入費用も軽減できる利点もあります。
また、家族が自然と顔を合わせる機会が増えるため、親世帯の健康や日常の様子が把握しやすいのも特徴として挙げられます。親世帯が高齢の場合、安心感を得やすい点は魅力のひとつといえるでしょう。
一方、プライバシーの確保が難しく、生活音や時間の違いがストレスとなる可能性があります。友人を気軽に招くのが難しいと感じる場合もあるでしょう。完全共有型は、費用面での負担が軽く、家族間のつながりを深めたい人に適した間取りといえます。
土地ありの場合!二世帯住宅の建築費用の相場
ここでは、土地ありの場合の費用相場を以下の場合に分けて解説します。
- 土地ありの完全分離型の場合
- 土地ありの一部共有型の場合
- 土地ありの完全共有型の場合
費用相場を解説した後、土地選びのメリットについても紹介します。
土地ありの完全分離型の場合
土地ありの場合、完全分離型の二世帯住宅を建てる費用は2,900万~5,500万円程度が目安です。親世帯と子世帯の生活空間を完全に独立させるため、玄関やキッチンだけでなく、リビングや浴室、トイレなどの設備をそれぞれ設置しなければなりません。
こうした特徴から、ほかの間取りと比較して高額な建築費となる傾向があります。住宅金融支援機構の調査によると、岡山県における注文住宅の平均建築費用は約3,900万円で、住宅面積は約122.2m2(約37坪)であることが明らかになっています。
出典:「2023年度集計表 注文住宅」(住宅金融支援機構)(https://www.jhf.go.jp/about/research/2023.html)を加工して作成
完全分離型は建築コストが高い反面、快適な生活環境を手に入れられる選択肢といえるでしょう。
土地ありの一部共有型の場合
一部共有型の費用相場は、2,200万~4,500万円程度です。設備や建材のグレード、設計内容によって金額に幅があります。また、共有部分の数によっても金額は変動します。たとえば、浴室やトイレを世帯ごとに設ける場合は、その分コストも高くなるでしょう。
しかし、完全分離型に比べて共有部分があるため、コストを抑えやすいです。ただし、生活のなかで気遣いやルール作りが求められることもあるでしょう。たとえば、掃除や設備の使用時間、生活費の分担は、事前に明確な取り決めが必要です。
土地ありの完全共有型の場合
土地ありの完全共有型の建築費用相場は、2,000万~4,000万円程度です。寝室のみを世帯ごとに設けるシンプルな間取りが多く、設備費用をとくに抑えやすいのが特徴です。
加えて、建築費や維持費の負担が少ない点も魅力といえます。各設備をひとつにまとめるため、光熱費や生活家電の購入費用も削減され、経済的なメリットが際立ちます。
一方で、生活空間が完全に重なるため、生活リズムが異なると夜中に足音で目を覚ますなど、ストレスを感じる可能性も考えられるでしょう。したがって、生活音が響きづらくなるように工夫を施すといった対策が求められます。
土地ありのメリット
最大のメリットは、土地の取得費用がかからない点です。たとえば、親世帯がすでに所有している土地に二世帯住宅を建築する場合、土地取得費用がかからないため、経済的な負担を大きく軽減できます。
新たに土地を購入する必要がない分、住宅そのものの建築費用に予算を充てられるのもメリットのひとつです。また、土地ありの状況では、利便性や思い出のある場所に住み続けられる精神的な安心感も得られます。
さらに、地元のコミュニティや周辺環境を変えずに暮らせる利点もあります。慣れ親しんだ環境で過ごせるため、親世帯・子世帯ともに新生活へのストレスが少ないでしょう。
土地なしの場合!二世帯住宅の建築費用の相場
続いて、土地なしの相場を以下の場合に分けて紹介します。
- 土地なしの完全分離型の場合
- 土地なしの一部共有型の場合
- 土地なしの完全共有型の場合
岡山県の土地相場もあわせて紹介しますので、参考にしてください。
土地なしの完全分離型の場合
土地なし・完全分離型の費用は3,900万〜6,500万円が目安です。土地を所有していない状態で完全分離型の二世帯住宅を建築する場合、土地取得費が加わるため、全体の費用は大きくなります。
住宅金融支援機構の調査によると、岡山県における土地取得費の平均は約1,000万円前後で、敷地面積の平均は249m2(約75坪)です。
出典:「2023年度集計表 土地付注文住宅」(住宅金融支援機構)(https://www.jhf.go.jp/about/research/2023.html)を加工して作成
土地取得費の平均である1,000万円を建築費の相場に加えると、上記の金額が算出されます。土地購入費に関しては、土地の広さや立地によって地価が変動する点にも注意が必要です。とくに都市部では地価が高くなるため、予算計画を慎重に立てることが欠かせません。
土地なしで完全分離型の二世帯住宅を建設する場合、予算をうまく活用するために土地選びや重視したいポイントなどを考え、メリハリをつけることが重要です。
土地なしの一部共有型の場合
一部共有型の二世帯住宅を建築する際、建物自体にかかる費用の相場は2,200万~4,500万円程度です。これに土地取得費の約1,000万円を加えた3,200万~5,500万円程度が土地なしで一部共有型の二世帯住宅を建てる費用相場です。
完全分離型と比較すると、コストは抑えやすい傾向にあります。間取りや設備などで金額は変動するため、どちらの世帯もあまり重視していない箇所は、グレードを下げるとよいでしょう。
土地なしの完全共有型の場合
完全共有型の二世帯住宅の建築費用は2,000万~4,000万円が一般的な目安です。土地を所有していない場合、上記の金額に土地取得費として約1,000万円を加算されるため、総費用は3,000万~5,000万円程度が相場です。
完全共有型も一部共有型と同様に、設備などのグレードによって金額はまったく異なります。両世帯が利用するリビングや水回り、玄関などはこだわる一方、それぞれが利用する部分は少しグレードを下げるなどの工夫をするとよいでしょう。
これにより、価格と性能のバランスが取れた二世帯住宅を実現しやすくなります。
岡山県の土地相場
岡山県の「令和6年地価公示の概要」によると、平均地価は1m2あたり67,700円となっています。用途別に見ると、以下のとおりです。
住宅地:45,900円
宅地見込み地:12,900円
商業地:129,300円
工業地:25,100円
なお、前年と比較して、住宅地や工業地はわずかながら上昇傾向にあります。
出典:「令和6年地価公示の概要」(岡山県庁)(https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/905487_8639887_misc.pdf#page=4)
住宅地では宅地見込地が12,900円と比較的低価格な一方、商業地は用途の特性から最も高い水準を維持しています。全体的な地価の平均も67,700円と安定しており、岡山県は土地取得において、全国的に見ても手頃な地域のひとつといえるでしょう。
土地を購入する際は、エリアごとの地価動向を把握し、用途や予算に合わせた適切な場所を選ぶことが重要です。
二世帯住宅の建築費用を抑える方法
費用を抑える方法は、以下のとおりです。
- 建材や素材を見直す
- 水回りは1か所にまとめる
- シンプルな外観と間取りを選ぶ
- 間取りを工夫する
- 減税制度や補助金制度を活用する
コストを抑えるそれぞれの方法について解説します。
建材や素材を見直す
二世帯住宅の建築費用を抑えるには、建材や素材のグレードを見直すのが効果的です。とくに内装は、多くの方がこだわりたい部分であり、気づかぬうちにコストが膨らんでしまうケースは少なくありません。
壁や床、ドアといった主要な部分は、デザインや仕様をシンプルにし、統一することで費用を効率的に抑えられます。壁紙は、最初は手頃な素材やデザインを選び、将来的にリフォームすることもおすすめです。
キッチンや浴室などの設備も「どうしてもこだわりたい要素」と「そうでない要素」をしっかり整理しておけば、大幅なコストダウンが見込めるでしょう。また、DIYを取り入れれば、コストを抑えつつオリジナルの空間を作ることも可能です。
水回りは1箇所にまとめる
二世帯住宅の建築費を抑えるためには、水回りを1か所に集約することが有効です。浴室やキッチン、トイレといった設備を近接して配置すれば、配管をシンプルにまとめられ、その結果、施工費や材料費を削減できます。
とくに完全分離型では、左右対称や上下階に揃える設計にすることで、効率的な配管が可能です。また、1階と2階に水回りを分ける場合でも、上下の位置を揃えれば、配管の無駄が省けるため、価格を抑えやすくなります。
設備を共有する一部共有型では、浴室やキッチンを共用にすると、より大きなコストダウンが期待できるでしょう。さらに、浴室乾燥機や床暖房といったオプション設備の必要性を家族間でしっかりと検討することも重要です。
シンプルな外観と間取りを選ぶ
建築費を抑えるためには、外観や間取りをシンプルにする手法も効果的です。複雑なデザインや装飾は、必要な建材の量や加工にかかる手間が増えるため、その分コストが高くなりやすい傾向にあります。
とくに、屋根の形状には注意が必要です。複雑な形ではなく、切妻や片流れのようなシンプルな形を選べば、施工費を削減できます。
また、間取りでも正方形や長方形に近いシンプルな形状を意識しましょう。このような形状であれば、無駄な空間が減る分、資材コストを抑えられるうえに、耐震性の向上も期待できます。
動線を考慮し、余計な廊下や仕切りを減らした設計を取り入れるのもよいでしょう。設計の段階で必要最低限の設備や部屋数を絞り込むことで、コストを削減しやすくなります。
間取りを工夫する
建築費を抑えるには、間取りの工夫が欠かせません。二世帯住宅では、部屋数を必要最小限に絞ることでコスト削減が可能です。
たとえば、リビングや客間を共用にすれば、個別の部屋を減らせるでしょう。玄関や水回りを共用にする方法も効果的ですが、利用時間が重なると混雑が生じる可能性があるため、慎重な判断が求められます。
さらに、廊下や仕切りを少なくしたシンプルな設計にすると、壁やドアにかかる費用を削減できるうえ、開放的な空間が生まれます。一つひとつの部屋を広く確保することで、快適性とコストカットを両立させられるでしょう。
また、収納スペースを分散せず、ファミリークローゼットとして1か所に集約するのもおすすめです。効率的に空間を活用しながら、建築費用を抑えられます。
二世帯住宅の設計では、共有と個別のバランスを考慮し、無駄な空間を最小限に抑えることが経済的な住まいづくりのカギとなります。
減税制度や補助金制度を活用する
二世帯住宅の建築費を抑えるために、国や自治体が提供する減税制度や補助金制度の活用も視野に入れましょう。バリアフリーやエコ住宅などの基準を満たせば、リフォームや新築に対する補助金が支給されるケースがあります。
たとえば、太陽光発電や省エネ性能の高い設備を導入すると、補助金が受け取れるだけでなく、ランニングコストも削減可能です。また、自治体独自の支援制度も見逃せません。
自治体ごとに異なる補助金や助成金が設定されている可能性があるため、公式ホームページなどで情報を収集し、うまく活用しましょう。
二世帯住宅は減税制度を活用してコストを削減!
二世帯住宅では、減税制度が活用できます。まずは、二世帯住宅における減税制度について解説しましょう。
二世帯住宅における減税制度とは
二世帯住宅を新築する際には、各種減税措置を利用すれば、税負担を軽減できます。主な減税制度は、以下のとおりです。
- 住宅ローン控除
- 贈与税の非課税措置
- 不動産取得税の軽減措置
- 固定資産税の減額措置
- 登録免許税の軽減措置
住宅ローン控除は、一定の要件を満たす住宅に対して、ローン残高の一部が所得税から控除される制度です。二世帯住宅の場合、世帯ごとの居住スペースが明確に分かれていれば、ローンを借りたそれぞれの世帯が控除を受けられます。
さらに、親から子への住宅資金贈与は、一定額まで非課税となる特例があります。
出典:「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm)
この制度を活用すれば、贈与税の負担を軽減しながら、建築費用を工面できるでしょう。
また、不動産取得税や固定資産税、登録免許税についても軽減措置が設けられています。これらの制度を組み合わせて活用すれば、家計への負担を軽減できるでしょう。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を購入・贈与などで取得した際に課される地方税です。不動産の引き渡しから約3〜6か月後に納税通知書が送付され、納付が求められます。
税額は「不動産の価格(課税標準)×税率(3%)」という計算式で算出されます。しかし、新築住宅には税負担を軽減する措置が適用されます。
具体的には、新築住宅の場合は住宅部分の評価額から1,200万円を控除した額に税率を掛けて計算されます。認定長期優良住宅に該当する場合、控除額は1,300万円に引き上げられるため、より大きな減税効果を得ることが可能です。
二世帯住宅の場合、構造上および利用上の独立性が認められたうえで区分登記が行われていれば、二世帯分の控除が受けられます。その場合、最大2,400万円、認定長期優良住宅であれば2,600万円の控除が可能です。
出典:「不動産取得税 Q&A」(岡山県庁)(https://www.pref.okayama.jp/page/detail-37548.html)
制度を正しく理解し、適切に手続きすることで、不動産取得税の負担を軽減できるでしょう。
固定資産税
固定資産税は、1月1日時点で土地や建物を所有している人に課される地方税です。不動産を保有している限り毎年支払う必要があります。
税額は課税評価額に税率1.4%を乗じて算出されます。しかし、住宅用地や新築住宅には、税負担を軽減する措置が適用されます。
土地は、住宅1戸あたり200m2までの部分を「小規模住宅用地」とし、課税評価額が6分の1に軽減されます。また、200m2を超える住宅用地では課税評価額が3分の1に引き下げられます。
出典:「土地に対する課税のしくみ」(岡山県庁)(https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000005118.html)
建物に対しては、新築住宅の場合、床面積が50m2以上280m2以下であれば、120m2までの部分において固定資産税が半額になります。軽減措置は、新築から3年間適用されますが、認定長期優良住宅であれば5年間に延長されるのが特徴です。
出典:「家屋に対する課税のしくみ」(岡山県庁)(https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000005106.html)
条件を正確に把握して適切に申請すれば、長期的な固定資産税の負担を軽減できるでしょう。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記手続きを行う際に課せられる税金です。新築住宅を建築する際には、以下の登記に税額が発生します。
- 土地取得時の所有権移転登記
- 建物に関する所有権保存登記
- 住宅ローンを利用する場合の抵当権設定登記
通常の税率(本則)に対し、新築住宅には軽減措置が適用されるため、負担を軽減することが可能です。具体的には、土地の所有権移転登記では2.0%から1.5%に、建物の所有権保存登記では0.4%から0.15%に軽減されます。
また、住宅ローンに伴う抵当権設定登記は、通常0.4%の税率が0.1%に引き下げられます。軽減措置は令和8年3月31日までの期間限定のため、適用期間内に手続きを進めることが重要です。
出典:「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf)
助成金・補助金
国や地方自治体が提供する助成金や補助金を利用することは、二世帯住宅の建築費用を削減する効果的な手段です。こうした制度はエコ性能が高い住宅の新築やバリアフリー設計の実施など、特定の条件を満たす工事に対して経済的な支援を提供します。
施策の詳細や対象条件は時期や自治体によって異なるため、計画を立てる段階で必ず最新の情報を確認しましょう。申請期限や具体的な手続き方法についても、事前に把握しておくことが重要です。
二世帯住宅でお悩みの方は「岡山県の不動産売買情報サイト『岡山で暮らす』」にご相談ください。土地探しや不動産会社紹介も行っておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
まとめ
二世帯住宅を検討する際、建築費用や土地の有無、住宅のタイプに応じて費用が異なることを理解することが大切です。完全分離型や一部共有型、完全共有型それぞれの特徴を把握し、ライフスタイルに合った選択肢を見つけることが求められます。
建築費用を抑えるためには、建材や間取りを工夫する手法が効果的です。さらに、減税制度や補助金を活用すれば、コストや税負担を軽減できます。
岡山県で理想の二世帯住宅を手に入れたいとお考えの方は「岡山県の不動産売買情報サイト『岡山で暮らす』」にご相談ください。当社は岡山の住宅業界で豊富な経験を持ち、不動産会社や工務店、ハウスメーカーをご紹介しています。
家族全員が満足できる住まいづくりを全力でサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。